
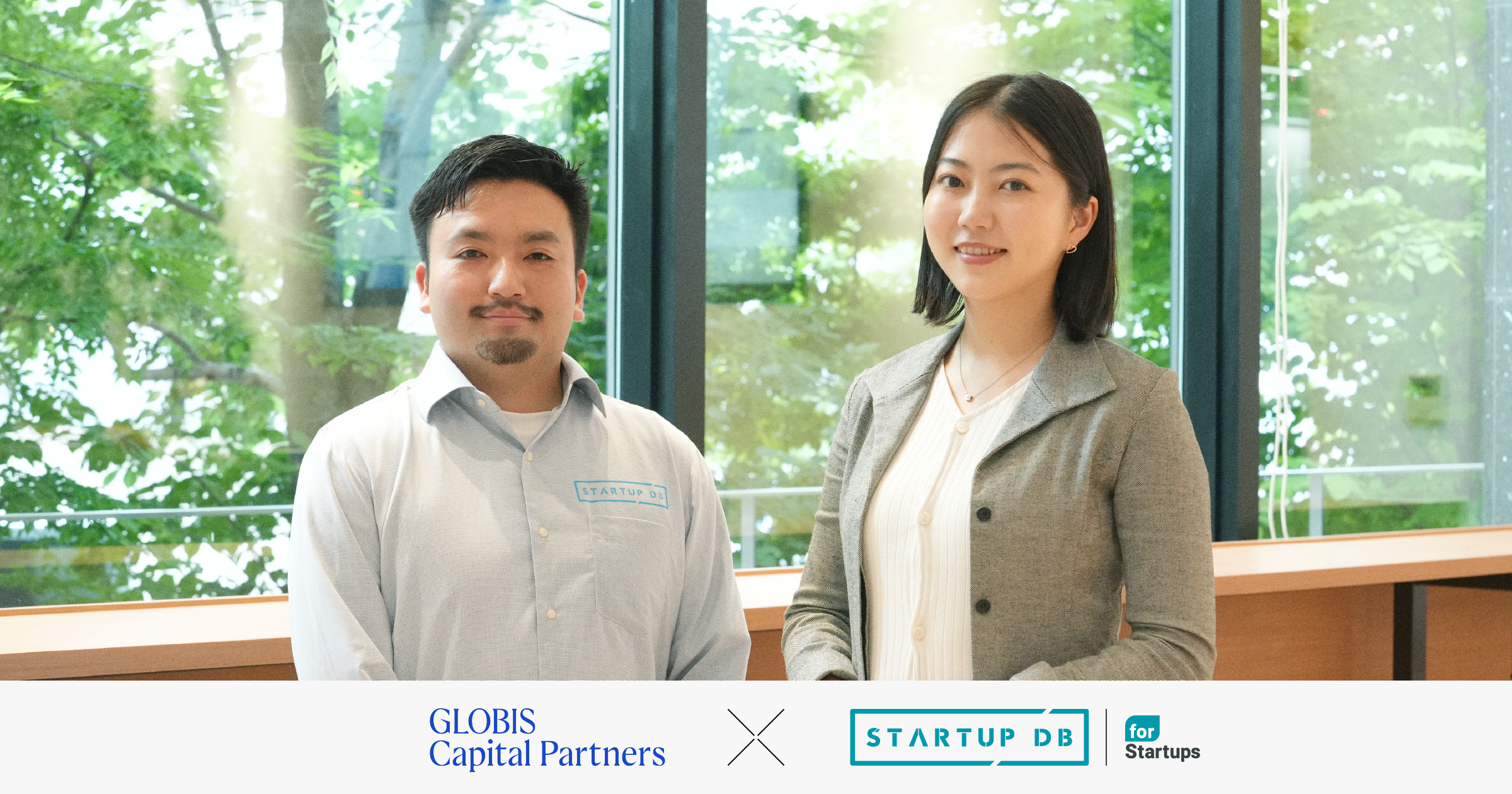
1996年の創業以来、単なる資金提供者に留まらず、経営ノウハウやネットワーク、人材といった多面的なリソースを提供する「ハンズオン型」VCのパイオニアとして、日本のスタートアップエコシステムの発展に大きく貢献してきたグロービス・キャピタル・パートナーズ。2023年3月には7号ファンドがファイナルクローズしました。今回はキャピタリストとして活躍されている工藤 真由様にお話しを伺いました。

工藤様:
グロービス・キャピタル・パートナーズ(以下、GCP)には、キャピタリストとして入社しました。
投資先候補のスタートアップを探す「ソーシング」、出資の意思決定を行う「投資検討・デューデリジェンス(DD)」、最終的なIPOやM&Aといったイグジットまで伴走する「経営支援・バリューアップ」まで、全面的にスタートアップを支援しています。
工藤様:
現在、7号ファンド運用中で2023年の3月にファイナルクローズしたファンドになっています。主にこのファンドから出資をしており、基本的にリード投資家として出資を行っています。
727億円というサイズが大きいファンドですが、集中投資という形で、将来的な企業価値が数千億円を目指せるようなテーマに投資していきたいと考えています。
シリーズA前後で出資させて頂く機会が多いですが、それよりも前のタイミングでも起業家とお会いするのはもちろん、シード期に数千万円単位でも出資しているので、比較的初期からタッチポイントを持たせて頂いています。
その後、マイルストンに合わせて、追加出資も積極的に行っています。
そのため、最初の投資から7〜10年の単位で長期間ご一緒させて頂くケースが多いです。
工藤様:
当社としては、大きく分けて3つあると考えています。
1つ目は「ファイナンス面のサポート」です。
大きなチャレンジをすると、その分の資金が必要になるので、ファイナンス面でのサポートは不可欠です。
先ほどご紹介したように、GCPは幅広い金額レンジでの出資に対応しており、スタートアップの成長フェーズに応じた柔軟な投資が可能です。
2つ目は「ディスカッションパートナーとしての伴走」です。
我々はリード投資家として出資させていただき、多くの場合で外部取締役にも入ります。
投資担当は経営陣の一員として、次回ラウンドやIPO/M&Aに向けたディスカッションしていくパートナーでありたいと考えています。
「GCP-X」という組織戦略に特化した支援チームも社内で組成しているので、彼らとも連携して、事業・組織両面から各社のニーズに合わせて全面的にバックアップしています。
また、1996年から独立系VCとして投資活動を行っていく中で、様々なスタートアップの成長ストーリーを見てきました。
そのような過程でファンドとして蓄積してきたナレッジも社内で共有し合い、投資先のスタートアップに還元していきたいと思っています。
3つ目は「グロービスのコミュニティ」です。
グロービスでは、経営大学院や法人研修、日本版ダボス会議と呼ばれる「G1」というプラットフォームなど多岐にわたる事業を経営しています。
GCPは機関投資家をLPとしており、日々の意思決定は切り分けて行っているものの、グロービスとも適宜連携を図っています。
例えばG1は、政・官・財や文化活動・NPO団体など様々なリーダーが集うコミュニティです。投資先起業家にもニーズに合わせて参加していただき、コミュニティを活かした事業成長やネットワーク作りを支援しています。

工藤様:
明確には決まっていません。
その時々で自立的に「今、自分が何に興味があるのか」「今、どのテーマに投資すべきなのか」を探しに行くスタイルです。
私の場合は「日本の大きな産業を強くアップデートし、海外でも戦えるような日本企業を作りたい」という想いがあります。
自分の軸を持ちながら、時代の流れや今後を見据えて柔軟に活動するように心がけています。
工藤様:
様々な手法を組み合わせていますが、大きくは「アウトバウンド」と「インバウンド」に分かれます。
アウトバウンドは、その時に自分が興味あるテーマに根差した事業を展開しているスタートアップにタッチポイントを作りに行く活動をしています。
具体的には、起業家が集まるイベントに参加したり、自分自身でイベントを企画したり、時にはSNSでDMを送ってコンタクトを取る時もあります。
インバウンドは、他社の投資家やエンジェル投資家などからご紹介を頂くケースです。
そのためにも、イベント登壇やSNSを通して「この分野に興味があるキャピタリスト」という認知をしてもらうために外部発信も積極的に行っています。
工藤様:
ネット上で得られる情報には限りがあるので、拾いきれていない情報があると考えています。
そのため、会いに行く範囲はあまり狭めすぎずに、機会を頂けるなら様々なスタートアップにお会いするようにしています。
様々なスタートアップとお会いし、私たちが見えていなかった視点やテーマを教えていただきながら、自身の投資仮説をアップデートしていくことを大事にしています。

工藤様:
導入前はリリース情報やSNSを参照し、スタートアップを探していました。
ただ、この探し方だと時間がかかるのと、見逃している企業があるという課題感がありました。
特に、創業期のスタートアップだとプレスリリースを出されていないケースもあるので、プレスリリースやSNSだけで、全て情報を網羅するのは限界があります。
そこで、投資テーマやシリーズを条件に、スタートアップを網羅的に可視化できる体制を構築する1つの方法として、STARTUP DBの導入に至りました。
工藤様:
基本的な使い方は以下の2つでして、
1つ目は、先ほどご紹介したようなソーシング活動をする上で、その時に興味があるテーマや業界をタグ/検索ワード/ラウンド/調達額などの条件で絞り込みを行い、スタートアップを一覧化する使い方です。
この一覧化する探索を行うことで、「見逃してしまう」という課題を解決することができます。
2つ目は、スタートアップとの面談前に、その企業をSTARTUP DBで検索し、事業概要/資金調達履歴/評価額/リリース情報を見るような使い方です。
スタートアップの事業概要をはじめとして、創業者の経歴や既存株主の情報、従業員数の伸び率などの今後の成長性を想像する上で重要な情報が1つのページにまとまっているので、個社の情報を分析する上でとても使いやすいです。
工藤様:
調査する目的がそれぞれ異なるので、場面によって使い分けています。
私が生成AIを使用する際は、より仮説ベースで領域を深堀しながら具体的な企業を探しに行きます。
深める過程で「こういう企業」と絞っていくので、どうしても主観性が含まれてしまうんですよね。
もちろん主観を持つことは重要ですが、それに固執しすぎてしまうと、自分が知らない分野や技術に辿り着けないという機会損失になるケースもあります。
STARTUP DBでは、そのような主観性は排除した状態で探索することができます。
広く定義されているタグに紐づく企業を一覧で見ることで、自分が見ていなかった領域・企業に出会えることがあります。
なので、自分の考えを壁打ちする際には生成AIを使い、自分の知らない分野も含めてより俯瞰して企業を眺めたい場合にSTARTUP DBをよく見ますね。

工藤様:
各々のスタートアップが「いつ/どの投資家から/いくら資金調達して/どのくらいのバリュエーションがついているのか」という観点で情報を見ながら、資本政策や事業成長を推測するようにしています。
その上で、推察した仮説を基に、実際にスタートアップから直接資本政策や事業成長を聞いて、そのギャップを見ていますね。
資本政策の背景には、何かしらの戦略や意図があるんですよね。
こういうお金を入れたい、こういうプレイヤーを巻き込みたいなど、そこを聞くためにも事前情報として把握していると、議論の幅が広がりやすいと思っています。
私はスタートアップの方々とお話しする際には、何かしら仮説を立てながら会話をしたいので、そのための情報源としてもSTARTUP DBの情報を見ています。
工藤様:
見逃してしまうスタートアップが出てくるリスクがあると思います。
先ほどもお話ししたように、プレスリリースやSNSだけで情報収集すると、PRに力を入れきれていないスタートアップは見つけきれないんですよね。
特に私たちは創業初期のスタートアップを積極的に探しているので、なかなか情報が表に出ないことが多くあります。
そのため、STARTUP DBの情報の網羅性は、投資機会を最大化するためにも非常に重要だと考えています。

工藤様:
冒頭にお話ししましたように、私たちは大きなテーマにチャレンジしているスタートアップに投資していきたいと考えています。
その中で業界全体を変革するような動きが必要になりますが、事業会社が持っている資金、技術やネットワークなどのアセットと、スタートアップが組むことによって、業界を良い方向にする取り組みができると思うんですよね。
そういった形で業界全体や生活全体を良くしていこうという動きを事業会社の方々と一緒にできたら面白いと思いますし、投資家としてもご一緒できたら嬉しいです。
昨今では、事業会社とスタートアップの協業事例も増えてきていますが、事業内容やカルチャーが異なる企業同士が一緒に取り組むことは、依然としてハードルが高い部分もあるのではないかと感じています。
事業会社側には、IR的な観点からそこまで赤字は出せないといった背景もあると思いますし、スタートアップ側には、前例のない取り組みのためイメージができないこともあると思います。
そのためにも、私たちのような投資家やフォースタートアップスさんのような双方に繋がりがある企業が間に入って、潤滑油になっていけたら良いなと思っているので、カジュアルに皆さんとディスカッションしていきたいですね。

取材・執筆:久保田 裕也(for Startups, Inc.)
写真:佐々木 航平(for Startups, Inc.)

スタートアップとの事業共創を実現させるサービス『STARTUP DB ENTERPRISE』について、使い方はもちろんのこと、実例も含めてわかりやすくご紹介します。スタートアップ、オープンイノベーションに精通したフォースタートアップスが提供するデータベースサービスだからこそ、協業までご支援することが可能です。スタートアップ企業を網羅的に探索し、協業を実現したい事業会社/CVCの皆様におすすめです。
資料請求