
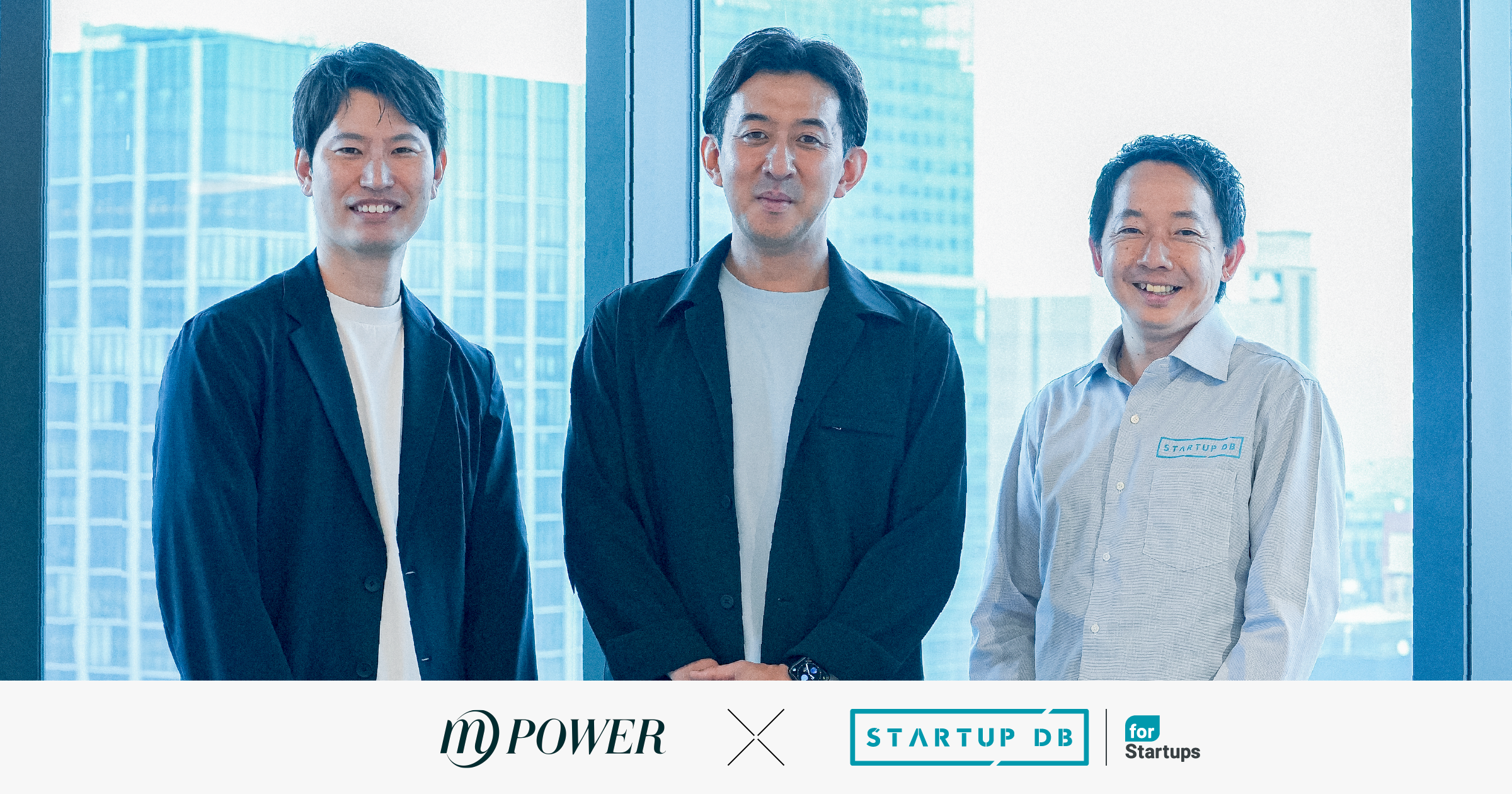
日本を拠点とするESG(Environment・Social・Governance)重視型のグローバル・ベンチャーキャピタルファンドとして、日本のベンチャーエコシステムにおいて地位を確立してるMPower Partners。2025年5月には2号ファンドを設立されました。今回は投資チームとして活躍されている深澤 優壽様、保坂 和博様に投資戦略やSTARTUP DBの活用状況についてお話しを伺いました。

深澤様:
私はパートナーという役割を担っており、スタートアップの「ソーシング/投資検討・デューデリジェンス(以下、DD)/投資実行」といった投資活動の全般と、投資後のバリューアップをサポートさせて頂く活動など、幅広く担当しております。
加えて、我々は投資活動を通してESGの観点を重視しているので、ポートフォリオに対して、ESGを意識したサポートも行っております。

保坂様:
私も同じ投資チームの一員なので業務内容は近く、投資活動に関わる全てのサイクルを担当しています。
具体的には、ソーシング/DD/契約周り/投資先のサポートなどに携わっています
私は、ファンドレイズのタイミングに入社したので、LP候補様向けのピッチ資料作成やファンド組成における資金調達も並行して行っておりました。
深澤様:
各企業のステージやミッションによっても変わってきますが、一般論としてスタートアップはリソースの問題もあり、なかなかESGに本腰を入れて取り組む余力が確保できないケースも多いのかなと思います。
一方で、我々が投資してるスタートアップは、主にミドルからレイトステージが中心になっており、今後数年での上場またはM&Aが期待されるような企業です。
そのため、スタートアップであっても、ESGの取り組みについてディスカッションさせて頂いています。
意識高く取り組まれているスタートアップでも、SocialとGovernanceはしっかりしているけれど、Environmentが弱いとか、ESGのフレームワークに沿って、我々を壁打ち相手にしながら、ブラッシュアップしていくコミュニケーションをしています。
また、「マテリアリティ」という会社としてのESGの優先順位を決めるプロセスがあります。投資先のスタートアップには、このマテリアリティを策定頂くことを前提に投資しています。我々も策定における議論に参加しながら、ロードマップやアクションプランまで反映する支援を行っています。
保坂様:
弊社の投資検討では、DDの中にESG DDというプロセスがあります。
投資検討しているスタートアップが、例えば組織の多様性やガバナンスといった点において、それぞれどのような状況にあるのかを把握した上で、弊社と目指すビジョンや会社組織のあり方が一致しているかどうかを確認してから投資を実行しています。
よくある誤解として「MPowerさんってインパクトファンドなんですよね?」と言われることがあるのですが、その点は明確に違います。
考え方としては、 弊社はESGを投資先の事業成長を助け、企業価値を最大化するためのフレームワークとして考えており、投資領域を絞るためのフィルターという位置づけではないので、 例えばこれまで AI / SaaS / リーガルテック / サイバーセキュリティ / ディープテック など一見するとESGとの関連が薄そうな領域も含め、幅広い領域に投資をしていますし、インパクトファンドとは考え方が異なります。
あくまでも、独立系VCとして財務リターン追求するためのツールの1つに、ESGのフレームワークを持っているという形です。
そのため、あくまでも投資先の成長にとって有効的なツールとして機能しうる範囲においてESGの考え方を活用しましょうという考え方ですし、それが企業成長の足枷になるのであれば、弊社の方でそれを押し付けるようなことはありません。
投資先の長期的かつ持続的な成長をサポートすることが一番の目的ですのでそこは明確にお伝えさせてください。

深澤様:
確かに、それは論点としてあると思います。
社員が数十人のスタートアップでは、ESGの取り組みにリソースを割くよりも、まずはプロダクトを作って売上を立てることが優先されます。
そのような状況で、弊社もそこに対して多くのリソース割いてくださいというのも、ちょっと違うのかなと思います。
一方で、創業1,2年目の企業でも、 次の10年で大きな会社になることを目指していると思います。
そのため、そこから逆算して創業時から自分たちの会社が、世の中にどう貢献していくのかは事前に考えておく必要があります。
創業初期から意識しておかないと、10年経った後に全く人材や考え方の多様性がない企業や、ガバナンスが効かない企業になってしまうと、そこから軌道修正するのは時間がかかります。
ESGを意識して反映している企業の方が、中長期的な事業成長を実現しているという調査結果もあります。実際に弊社の投資先でも、ダイバーシティやガバナンス領域で課題を持っており、弊社がサポートさせて頂いた結果、組織が強くなった事例もあります。
保坂様:
ESGと聞くと、現場や日々の業務と関連性の薄い大きなコンセプトという印象を持たれるかもしれませんが、ESGやマテリアリティを策定する過程で「会社としてどのようなミッションを掲げるのか」「どのような組織カルチャーを醸成していきたいか」「社会にどんなバリューを届けたいか」などを社内で議論することになります。
これはビジョン策定に近いため、それはアーリーかレイターかはあまり関係ありません。
むしろ早い方がしっかり組織として方向性を定められるので、事業成長や社員のモチベーション、 採用活動、資金調達など、様々な局面でポジティブに機能すると考えています。
深澤様:
多くのVCと同様に、我々からアプローチをするアウトバウンドとお問い合わせを頂くインバウンドの手法を、それぞれバランスを取って活動しています。
MPowerは、コンセプトが特徴的なVCだと捉えています。
そのため、我々の価値観に共感して「MPowerのような価値観を持った投資家に入っていただきたいです」といった形で、起業家の方から直接ご連絡をいただくこともありますし、投資家経由でご紹介頂くこともあります。
他の投資家からの紹介は一般的だと思いますが、我々の特徴としては「このスタートアップは MPowerさんにすごく合っていませんか?」というように、MPowerのことをご理解頂いた上でご紹介いただくケースが多くあります。
これだけではなく、テーマフィットがありそうなスタートアップに我々側からご連絡することもあります。
例えば、新しく立ち上がった2号ファンドでは「ジャパン・ダイナミズム」というテーマで、投資活動を行っています。これはESGという枠を超えて日本の強みを活かしながら、日本固有の課題を解決することを目指していくため、ディープテックやAIなど幅広く興味を持っており、このテーマに合うスタートアップを探索しています。

保坂様:
弊社は海外の企業にも投資しております。
チームメンバーにはグローバルのバックグラウンドを持つメンバーが揃っておりますので、弊社のネットワークにいる海外の投資家経由で投資先候補をご紹介を頂くケースもあります。
また、メインファンドではミドル・レイターステージのスタートアップに投資していますが、女性活躍推進というテーマ特化型の姉妹ファンド「WPower」を今年設立しました。
このファンドでは、テーマフィットするシード・アーリーステージのスタートアップに投資する予定で、MPowerとWPowerを合わせて、オールステージで投資実行できる体制になっています。
深澤様:
これはまさに大事なポイントです。
投資チームは個々人によってソーシングのスタイルは異なっており、それが強みだと考えています。
我々はダイバーシティを重視しているファンドですが、MPowerの社内でも同様で、個々人が多様なバックグランドを活かした手法で、チームのパフォーマンスを向上させています。
例えば、私はアメリカのネットワークを持っていますが、保坂さんはヨーロッパや東南アジアのネットワークを持っていたりします。
このように各々のバックグラウンドの多様性を活かして、ソーシング活動を行っているので、ソーシングの方法も異なります。
深澤様:
データベースは以前から導入していましたが、活用しきれていないという課題があり、他のサービスを比較検討してみようということになりました。
その中で、以前から名前を聞いたことがあったSTARTUP DBをトライアルをして、私も含めてチーム全員で使ってみました。
STARTUP DBを導入時に評価したポイントは3つあります。
1つ目に、使ってみてまず感じたのは「画面の見やすさ」でした。
非常に直感的で、スタートアップの情報がスッと目に入ってくる設計になっていて、これは見やすいと思ったのが第一印象でした。
2つ目に、「スタートアップの掲載社数と更新頻度」です。
当然ですが、データベースとして使用する中では、見た目だけではなくて中身も重要です。
そこで、「スタートアップが何社掲載されているのか?」「シードやアーリーステージの企業でも漏れなく掲載されているのか?」といった観点で、営業担当の方から話を聞いたり、実際に自分たちで検索をかけて件数を確認しました。
調査した結果、データベースとして「事業概要/資金調達履歴/評価額/リリース情報」などの情報が網羅されていると自分たちの目で確認できました。
また、様々なデータベースの毎月追加される掲載社数を比較したとき、STARTUP DBが急速に増えていたので「これは積極的にいろんなスタートアップを探しながらリサーチをして、登録件数を増やしているんだな」と思いました。
加えて、創業して半年/1年/3年/5年といった、いわゆる創業年数に応じた掲載社数の比較も行いましたが、創業年数が若い企業の登録社数に関しては、STARTUP DBの方が明確に多いという結果になりました。
私たちとしては、創業して間もない企業をスピーディーに探したいというニーズもあるので、STARTUP DBを活用することで新しい会社の情報がどんどん増えていく点が魅力的でした。
3つ目に、「新機能開発予定のスケジュール感」です。 当時のご説明の中で印象的だったのが、非常に積極的に機能開発を進めていらっしゃるという姿勢でした。 もちろん、その時点で使える機能の説明もありましたが「半年以内にこういう機能が追加される予定です」といった、今後のロードマップ的な説明もあり、機能追加や使いやすさの改善に継続的に取り組まれていることが伝わってきました。

保坂様:
スタートアップと面談する前や、アウトバウンドで連絡をする企業を決める際には、STARTUP DBを使っています。
主に以下の3つの情報を見ています。
1つ目は、「事業概要文」です。
スタートアップの事業内容が端的にまとまっていて分かりやすいので、そこを読んで自分の興味がある分野かという最初のフィルターとして使っています。
2つ目は、「資金調達の履歴」です。
どのステージで、どの投資家が入っているかを中心に見ています。
これは投資検討の際の重要な要素だと考えていて、トップティアと呼ばれるような投資家が入っているかどうかは、評価の指標の一つになります。
それに加えて、直近で資金調達しているかも確認します。
例えば、過去1年〜1年半前に調達していたとしたら「そろそろ資金調達するかもしれない」というような推測をすることができ、次の資金調達のタイミングを予測することにも活かしています。
3つ目は、「従業員数の推移」です。
従業員数の推移が右肩上がりになっていれば、事業が成長しているという1つの指標になります。
従業員数によっては、新たな資金調達ニーズがある可能性もあります。そのようなデータで見えるものから仮説を立てて、普段の業務に活かしています。
保坂様:
弊社が提示した条件を元に、約100社のスタートアップをリストアップして頂きました。
その中には、これまで弊社が知らなかったが、ファンドのテーマに合っていて、かつ資金調達のタイミングも合いそうな企業を見つけることができました。
我々は少人数のチームでやっているので、日本に存在するスタートアップを全て網羅的にカバーできているわけではありませんし、見逃している部分もあると思っています。
だからこそ、第三者の視点から一定の基準に沿ってリストアップしてもらえることで、これまでカバーできていなかった領域や、テーマに合う企業だが見落としていたところに気づくことができます。
そこが一番期待していた部分ですし、今後も活用していこうと思っています。
保坂様:
そうですね、やっぱりソーシングってすごく大事なんですよね。
ソーシングは投資活動の核になる部分で、自分たちのネットワークを使いながら、デスクトップのリサーチだけでは掴めないような企業と、ウェットな関係性を作っていくことが中長期的に見てもとても重要です。
その上で、STARTUP DBは、自分たちのネットワークだけでは補足しきれなかった企業を網羅的にカバーできるという意味で、とても重要な補完的役割を果たしてくれていると思っています。
深澤様:
我々としても、事業会社の方々とコラボレーションしながら、新しい事業を育てていきたいと考えています。
投資先には、最終的にはユニコーン、あるいは数千億円以上の価値を持つような大きな会社に育っていってほしいという思いがあります。
事業会社も大きなインパクトを出したいという想いをお持ちだと思いますので、その点で私たちの目指す方向性は一致しています。
我々は独立系VCとして、ファイナンス支援やバリューアップ支援に取り組みますが、事業会社が持っている技術力、営業チャネル、顧客基盤などの様々なノウハウを、スタートアップの成長のために活用して頂けるとありがたいと思っています。
スタートアップが10倍⇨100倍⇨1000倍とスケールしていくことで、それが最終的には事業会社の企業価値の向上にもつながると信じています。
また、我々は現在の投資先や今後投資する分野についても、オープンに情報を共有しています。
まだ接点を持てていない企業様や業界もたくさんあると思っていますので、もしご興味があればぜひお気軽にコンタクトをいただければと思います。
保坂様:
弊社は日本国内外で共同投資の実績があります。
例えば、弊社の投資先であるPhoenix Tailingsというスタートアップは、日本の大手事業会社様と一緒に共同投資を実施しています。
このように、日本・海外の両方で投資を行っており、今後はさらにファンドを拡張して、より積極的に取り組んでいく方針です。
また、弊社の投資先との事業提携という観点でもご一緒できる可能性があると思っています。
弊社が投資しているスタートアップはレイターステージが多く、既にPMFを達成し、成長の方向性が見えてきている企業を中心に投資しています。
そういった意味で、事業会社様とのシナジーもイメージしやすく、フェーズ的にも事業提携が進めやすいのではないかと考えています。
もしご関心を持っていただけそうでしたら、ぜひお気軽にお声がけいただければと思います。

取材・執筆:久保田 裕也(for Startups, Inc.)
写真:佐々木 航平(for Startups, Inc.)

スタートアップとの事業共創を実現させるサービス『STARTUP DB ENTERPRISE』について、使い方はもちろんのこと、実例も含めてわかりやすくご紹介します。スタートアップ、オープンイノベーションに精通したフォースタートアップスが提供するデータベースサービスだからこそ、協業までご支援することが可能です。スタートアップ企業を網羅的に探索し、協業を実現したい事業会社/CVCの皆様におすすめです。
資料請求